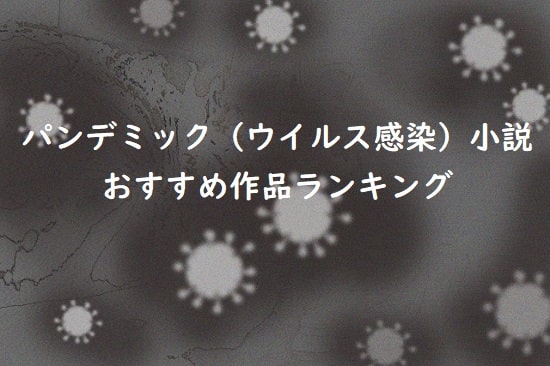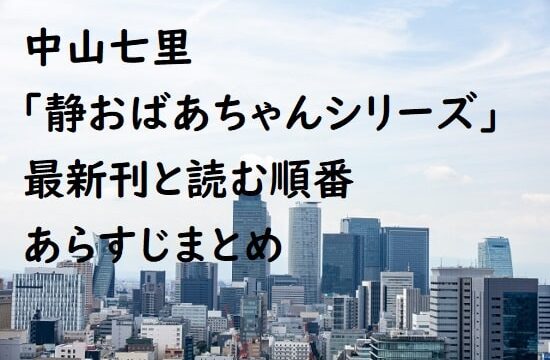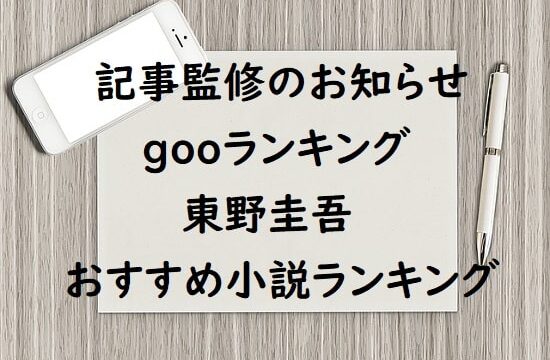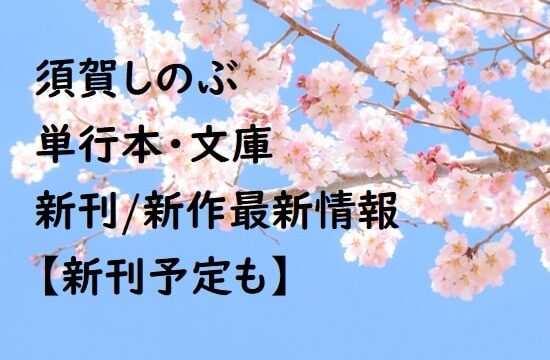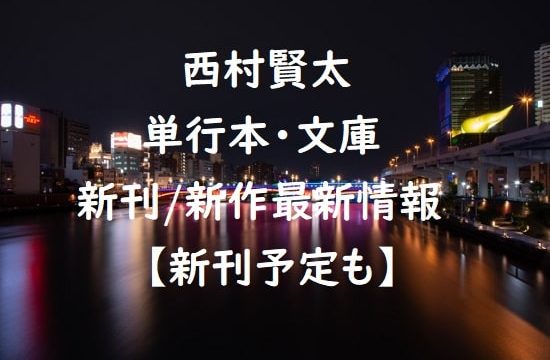[toc]
2020年は新型コロナウイルスの流行が世界的に広がっています。そして、パンデミックやウイルス感染の恐怖を描いた小説が、これまでにたくさん作られてきました。
そのような小説から学ぶこともあるかと思い、パンデミックやウイルスをテーマに扱った小説を紹介いたします。
パンデミック(ウイルス)小説のおすすめ作品10作
※10作としましたが、同率10位で2作挙げましたので実質11作となります
1.『ペスト』(カミュ/1969年)
<あらすじ>
アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。
今、話題になって売れている小説がこちら。
1969年と古い小説ですが、感染症であるペストの発生、そして闘う人間たち、さらには人間の心理にまで踏み込んだ内容に、多くの読者の心が掴まれます。
2.『首都感染』(高嶋哲夫/2010年)
<あらすじ>
二〇××年、中国でサッカー・ワールドカップが開催された。しかし、スタジアムから遠く離れた雲南省で致死率六〇%の強毒性インフルエンザが出現! 中国当局の封じ込めも破綻し、恐怖のウイルスがついに日本へと向かった。
検疫が破られ都内にも患者が発生。生き残りを賭け、空前絶後の“東京封鎖”作戦が始まった。
首都封鎖が現実味を帯びてきた昨今、まさにその内容そのもののストーリーを描いたのが本作。
中国発のウイルス(作中ではインフルエンザ)、封じ込めの失敗、検疫突破……まるで実際に起こっていることを追体験できるような内容に震えすら起きます。
3.『復活の日』(小松左京/1964年)
<あらすじ>
吹雪のアルプス山中で遭難機が発見された。傍には引き裂かれたジュラルミン製トランクの破片。中には、感染後70時間以内に生体の70%に急性心筋梗塞を引き起こし、残りも全身マヒで死に至らしめるMM菌があった。
春になり雪が解け始めると、ヨーロッパを走行中の俳優が心臓麻痺で突然死するなど、各地で奇妙な死亡事故が報告され始める―。
人類滅亡の日を目前に、残された人間が選択する道とは。著者渾身のSF長編。
小松左京によるパンデミック小説。
細菌による世界的な流行と、その後の人類の選択を描いた壮大な物語。こちらも古い作品ではありますが、現代に通じるものがあり、深く考えさせられるラストになっています。
4.『夏の災厄』(篠田節子/1995年)
<あらすじ>
平凡な郊外の町に、災いは舞い降りた。熱に浮かされ、痙攣を起こしながら倒れる住民が続出、日本脳炎と診断された。撲滅されたはずの伝染病がなぜ今頃蔓延するのか?
保健センターの職員による感染防止と原因究明は、後手にまわる行政の対応や大学病院の圧力に難航。その間にもウイルスは住人の肉体と精神を蝕み続け―。
20年も前から現代生活の脆さに警鐘を鳴らしていた戦慄のパンデミック・ミステリ!
篠田節子によるパンデミックをベースにしたミステリー。
こちらは伝染病(日本脳炎)が起きる謎だけでなく、後手後手となる行政、大学病院の圧力という、今もなお問題視されるであろう課題がリアルに描かれています。
5.『黒い春』(山田宗樹/2000年)
<あらすじ>
覚醒剤中毒死を疑われ監察医務院に運び込まれた遺体から未知の黒色胞子が発見された。そして翌年の五月、口から黒い粉を撤き散らしながら絶命する黒手病の犠牲者が全国各地で続出。
対応策を発見できない厚生省だったが、一人の歴史研究家に辿り着き解決の端緒を掴む。そして人類の命運を賭けた闘いが始まった―。傑作エンタテインメント巨編。
こちらは架空の「黒手病」という胞子が拡散して、病気を引き起こすというパンデミック小説。
打つ手が見つからないもどかしさと一筋の光。絶望の中に希望を見いだしていく過程が迫真的な描写で紡がれています。
6.『天使の囀り』(貴志祐介/1998年)
<あらすじ>
北島早苗は、ホスピスで終末期医療に携わる精神科医。恋人で作家の高梨は、病的な死恐怖症だったが、新聞社主催のアマゾン調査隊に参加してからは、人格が異様な変容を見せ、あれほど怖れていた『死』に魅せられたように、自殺してしまう。
さらに、調査隊の他のメンバーも、次々と異常な方法で自殺を遂げていることがわかる。アマゾンで、いったい何が起きたのか?
高梨が死の直前に残した「天使の囀りが聞こえる」という言葉は、何を意味するのか?
前人未到の恐怖が、あなたを襲う。
貴志祐介によるホラー小説。
アマゾン調査からの奇行による死亡という謎が、恐怖をそそるとともに、まるで自分が体験しているかのような現実感をもって読み進められます。
7.『生存者ゼロ』(安生正/2013年)
<あらすじ>
北海道根室半島沖の北太平洋に浮かぶ石油掘削基地で、職員全員が無残な死体となって発見された。救助に向かった陸上自衛官三等陸佐の廻田と、感染症学者の富樫博士らは、政府から被害拡大を阻止するよう命じられた。
北海道本島でも同様の事件が起こり、彼らはある法則を見出すが…。未曾有の危機に立ち向かう!
壮大なスケールで「未知の恐怖」との闘いを描くパニック・スリラー。
北海道で起きた謎の死亡事件が発端。
そこから導き出された意外な真相と対処方法に、ページを繰る手が止まりません。
8.『ホット・ゾーン』(リチャード・プレストン/2014年)
<あらすじ>
脅威の感染メカニズムから、ウィルス制圧に命をかけた医療関係者たちの戦いまで―—。再燃する「エボラ出血熱」のすべてを描ききった、手に汗にぎるノンフィクションが蘇ります。
「解説書としての分かりやすさ」と、「小説のように一気に読める面白さ」を兼ね備え、
日本をはじめとする全世界で大ベストセラーになった一冊です。
ノンフィクションなのですが、「小説のように読める」ということで取り上げました。
エボラ出血熱と闘う人々の奮闘を描いた本作は、手に汗握る展開で、まさに小説のよう。そして感染症の恐ろしさと、対策についても学ぶことができます。
9.『天冥の標 2 救世群』(小川一水/2010年)
<あらすじ>
西暦201X年、謎の疫病発生との報に、国立感染症研究所の児玉圭伍と矢来華奈子は、ミクロネシアの島国パラオへと向かう。そこで二人が目にしたのは、肌が赤く爛れ、目の周りに黒斑をもつリゾート客たちの無残な姿だった。
圭伍らの懸命な治療にもかかわらず次々に息絶えていく罹患者たち。感染源も不明なまま、事態は世界的なパンデミックへと拡大、人類の運命を大きく変えていく―
SF作家の小川一水によるパンデミック小説。
国立感染症研究所の所員が主人公が、謎の疫病と闘います。しかしそれはやがて世界的なパンデミックへと発展し……結末で人類はどうなるのか。唸らせられる作品です。
シリーズ物ですが独立した作品ですので、こちら単体で楽しめます。
10.『月の落とし子』(穂波了/2019年)
<あらすじ>
それは人間の進歩を証明する、栄光に満ちたミッションのはずだった―。新しい時代の有人月探査「オリオン計画」で、月面のシャクルトン・クレーターに降り立った宇宙飛行士が吐血して急死する。死因は正体不明のウィルスへの感染…!?
生き残ったクルーは地球への帰還を懸命に試みるが、残酷な運命に翻弄されて日本列島へ墜落する―致死性のウィルスと共に…。
空前絶後の墜落事故!そして未曾有のバイオハザード! 極限状況の中で、人間は人間自身を救い希望を見出すことができるのか。
クリスティー賞史上、最大のスケールで描かれる超災害ミステリ。
2019年11月という、コロナ騒動の直前に刊行された本作は、第9回アガサ・クリスティー賞受賞作品。
月で発見されたというウイルスが地球に……という展開で、パンデミックを引き起こしていく様はまさに現在進行形。
10.『H5N1 強毒性新型インフルエンザウイルス日本上陸のシナリオ』(岡田晴恵/2007年)
<あらすじ>
南の島で強毒性新型インフルエンザが発生した。感染した商社マン・木田は帰国4日後に死亡。感染症指定病院や保健所は急いでパンデミックに備えるが、瞬く間に野戦病院と化す。
R病院副院長・沢田他、医師の間に広がる絶望と疲弊、遂には治療中に息絶える者も。
科学的根拠を基にウイルス学の専門家が描いた完全シミュレーション型サイエンスノベル。
感染学者の岡田晴恵さんが小説を書いていました。
ということで話題の本書は、本格的なパンデミック小説。同率10位に挙げました。
さすがの知識と専門性により、具体的な描写が冴えています。壮絶な現場の状況を知るためにも、読んでおくと良い作品でしょう。
なお、岡田さんはもう一作、パンデミック小説を上梓しています。こちらは2009年の作品で、やや社会派よりの内容となっています。
まとめ
以上の11作を紹介してきました。
リアルな描写やパニックの様子等、パンデミックが起きた際にどうなるのか、どの作品も考えさせられることでしょう。
これらの小説を通して、ウイルスに対する恐怖だけでなく、何かしら学ぶことができれば幸いです。